Booksコーナー
※お好きな本のタイトルをクリックして下さい。その本に関する内容が、表示されます。
| 掲載月一覧 | 2025年4月|2025年3月|2025年2月|2025年1月|2024年12月|2024年11月| 2024年10月|2024年9月|2024年8月|2024年7月|2024年6月|2024年5月 |
Books目次へ△ |
|---|
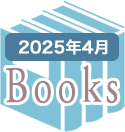
Booksコーナーでは、新刊本を中心に、小学校低学年から高学年向けのほか、保護者の方向けの本を紹介しています。学習の合い間などに、ぜひ読んでみてください。
『バイオミメティクスは、未来を変える』
-
- ◆橘悟=著
- ◆WAVE出版=刊
- ◆定価=1,980円(税込)
- ■対象:小学校高学年向け
「なぜこんなからだをしているの?」 そんな生き物への疑問が ものづくりのヒントになる!

「なぜ砂漠で生きられる生き物がいるのか」と、考えたことはありませんか。たとえばサハラ砂漠に生息するサハラギンアリ。その体毛には驚きの工夫があります。人の髪の毛などは切り口が円形ですが、このアリの体毛の切り口は三角形なのです。これによって降り注ぐ日光を上手に反射させて体温が上がるのを防いでいます。この仕組みをものづくりに活用したのが、熱をはね返すことのできる布製品です。この製品は自動車の内装部品への利用が進められていて、普及すれば車中での熱中症予防への効果が期待できます。
このように生き物のからだの構造や生態からヒントを得て開発した技術のことを「バイオミメティクス」といいます。人間はこれまでバイオミメティクスを使ってさまざまなものを作ってきました。たとえばトンネル工事の代表的な工法の一つ、シールド工法は、木材の内部を、穴を掘りながら進んでいくフナクイムシの観察から生まれました。またホッキョクグマの足の裏の構造は、雪道ですべらない画期的な冬用タイヤを開発するヒントになりました。
いかに生き物がいろいろなものづくりのヒントになっているか。その幅の広さには驚かされます。本書では事例を紹介するだけでなく、どのように生き物の能力を発見すればよいかなど、バイオミメティクスの見つけ方も教えてくれます。魚介類のウロコや吸盤、動物の毛、植物の葉や種子などはバイオミメティクスの宝庫です。
『ぼくのひみつのともだち』
-
- ◆フレヤ・ブラックウッド=作
- ◆椎名かおる=文
- ◆あすなろ書房=刊
- ◆定価=1,870円(税込)
- ■対象:小学校低学年向け
広がる森のイメージ 「絵を読む」絵本
朝、少年は着替えて学校に行く。いつもの道を通って。たった一人で。学校から帰ると仕事中のお父さんに見つからないよう、お盆に食べ物をのせて出て行く。小さな森にいる、とても大切な友だちに会いに。
少年と森の動物たちが主人公として登場する、オーストラリア発の絵本です。木がどんどん切られ、小さな森だけが残った少年の街。少しだけ残ったその大切な森も、失われそうになったとき、少年に奇跡が訪れます。文字はほんの少しです。イメージを膨らませながら、ゆっくり味わってください。
『たい焼き総選挙』
-
- ◆新井けいこ=作
- ◆いちろう=絵
- ◆あかね書房=刊
- ◆定価=1,430円(税込)
- ■対象:小学校中学年向け
大好きなお店を救うため 4年生チームが大活躍
拓都はたい焼きが大好き。今日も塾の帰りに親友を誘って、商店街の松丸堂へ。松丸堂はクラスメートのおばあちゃん、アユミさんが一人でやっている、たい焼き屋さんです。そのアユミさんがぎっくり腰でお店を休むと聞いて、拓都たちは大ショックです。
商店街のたい焼き屋さんのピンチに、拓都たちが応援に乗り出します。客足の変化を予測する難しさ、食品ロスを出さない工夫など、商売の厳しさを感じながらも、「総選挙」というアンケートを実施しながら、子どもたちがメニュー開発に挑戦していくという物語です。
『ミツツボアリをもとめて アボリジニ家族との旅』
-
- ◆今森光彦=文・写真
- ◆偕成社=刊
- ◆定価=1,760円(税込)
- ■対象:小学校低学年向け・小学校中学年向け・小学校高学年向け
祖先と同じ道を通って 彼らはアリをとりに行く
地面の色に埋もれて歩くオオトカゲ。シロアリの作った巨大な土の塔。そしておなかのツボに蜜をためてぶら下がる、ミツツボアリの不思議な姿。ここはオーストラリアの砂漠地帯です。この地で狩猟採集生活を送るアボリジニの家族と旅した著者が、その貴重な体験を写真とともにつづります。
小さな昆虫やワラビーなどの動物をとって食べ、石の色とは思えないあざやかな岩絵の具で体を飾って踊り、自然の恵みに感謝する生活。何万年も前から同じように暮らすアボリジニの営みを今日に伝える、驚異の写真絵本です。
『東北こわい物語』
-
- ◆みちのく童話会=編著
- ◆ふるやまたく=装画
- ◆おしのともこ=挿画
- ◆国土社=刊
- ◆定価=2,200円(税込)
- ■対象:小学校中学年向け・小学校高学年向け
雪女、鬼婆、亡霊… あなたのそばに、ほら
優しい老女姿の鬼婆が、旅人を食ってしまうという「安達ケ原の鬼婆」伝説。その舞台である福島県二本松市に遠足に行って以来、春陽の周りでは『安達ケ原の鬼婆』の本を手にした者は呪われる、といううわさが出始めました。そんなある日、春陽が靴箱を開けると、そこにはあの呪いの本が入っていました。
昔からの言い伝えは、現代生活のなかにも時折、見え隠れすることがあります。そうした六つの言い伝えを現代風にアレンジして紹介しています。東北6県の言い伝えにまつわるお話を集めた物語集です。
『もしもわたしがあの子なら』
-
- ◆ことさわみ=作
- ◆あわい=絵
- ◆ポプラ社=刊
- ◆定価=1,760円(税込)
- ■対象:小学校高学年向け
目が覚めたら、あこがれの あの子になっていた!?
塾の帰り道、ひとみはクラスいちばんの美少女で人気者のしずかとばったり。そこになんとクラスの嫌われ者、押川さんが乗る車が突っ込んできて…。気づけばひとみは病院のベッドの中。でも目の前にいるのはなぜか、しずかの母でした。
事故の瞬間、それまでほとんど接点のなかった3人の体が入れ替わるところから物語は始まります。ほかの人になることで、見える景色はどう変わるのでしょうか。自分を外から見ると、どんなことに気づくのでしょうか。他人の苦労や葛藤を知り、相手も自分もありのままを肯定できるようになります。
『沈黙』
-
- ◆遠藤周作=作
- ◆新潮社=刊
- ◆定価=781円(税込)
習った知識があるからこそ 興味を持って読める そこが歴史小説のおもしろさ

上大岡校校舎責任者わたしは学生時代によく外国を歩き回っていました。モロッコかイランだったかを旅していたとき、電車の窓から外を見ていたら、誰も見ていないなか、一人でイスラム教の礼拝をしている人の姿が目に入りました。そのときに思い出したのが、中学生のときに読んだ遠藤周作の「沈黙」です。
歴史が好きだった自分は、確か最初は手当たり次第に読んでいた歴史小説としてこの小説を読んだのですが、あらためて読み返すと、人と信仰とがテーマにされていることに気がつかされます。自分はそれほど宗教や信仰に対して真摯な人生を歩んできたわけではありませんが、旅をして回っているとイスラム教だけではなく、キリスト教や仏教が日常の生活にとけ込んだ生活を送っている人に多く会いました。自分と異なる価値観や考えを持つ人と、どのようにつき合っていくのかは、多様化が進む現代社会において大切なことだと考えるようになったきっかけの本です。
また、教科書で習う歴史は総論であって、細かい部分はわかりません。日本でキリスト教が禁止されていた時代に「踏み絵」があったことは歴史の授業で習いますが、それをリアルに感じ取れるのが歴史小説の優れたところです。踏めば命が助かるのになぜ踏まない人たちがいたのか。キリスト教徒への弾圧とは具体的にどんなものだったか。『沈黙』というタイトルはいったい何を意味するのか。それについてキリスト教を信仰していた遠藤周作がどのような答えを出しているのかは読んでみてのお楽しみです。非常に重いテーマですが、読みやすい文章を書く作家なので、歴史に興味がある人はきっと読めると思います。
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎













