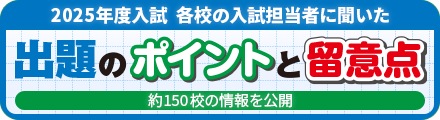さぴあインタビュー/関西情報
充実した授業と行事で育てる
共創力・自創力・発創力。
国公立大学への可能性を全員に
開明中学校・高等学校 校長 林 佳孝 先生

夜間歩行など多彩な行事で育てる
共創力・自創力・発創力

サピックス小学部
上本町校校舎責任者
中川 智史
立見 行事も多彩ですね。
林 行事は、授業と並ぶ本校の教育の柱です。日帰りのものや学校内で実施するものも含め、およそ3か月に2回のペースで行事があり、宿泊を伴うものも、各学年とも毎年2回あります。中1の場合は、入学式を終えた翌日から、1泊2日のオリエンテーション合宿を実施します。入学したばかりで友だちもいない状態ですが、山でハイキングや飯ごう炊さんをすることで、打ち解けた関係になれるのです。また、中1の夏には長野県の志賀高原で4泊5日の林間学校を行い、標高2295mの岩菅山(いわすげやま)に登ります。
中2になると、6月初旬に臨海理科実習があります。和歌山県の加太湾(かだわん)で海洋生物を採集するのですが、宿舎の広間でそれを顕微鏡で観察したり解剖したりして、最後はレポートにまとめて発表します。本校では、中学の理科を1分野(物理・化学)と2分野(生物・地学)に分けて展開していますが、2分野の中2の1学期前半の授業の多くは、この行事の準備にあてています。
そして、この臨海理科実習と同様に、本校が中学校開設以来ずっと続けている行事に、中3の3月に卒業記念行事として行う夜間歩行があります。これは、広島県生口島(いくちじま)の海洋センターから愛媛県今治市の糸山公園まで約43kmの「しまなみ海道」を、夜通し、14時間かけて歩くというもので、全員が参加します。教科学習には結びつかない行事ですが、つらくなったときに「みんなでやり切ろう!」という精神が身につくので、この行事の意味はとても大きいです。運動が苦手な生徒が、途中リタイアを何度も考えながらも、みんなに励まされ、本隊の最後尾から30分遅れで到着したこともありました。本人は歩き切ったことに感極まったのでしょう、ゴールした途端に号泣していました。その姿を見たときには、あらためて、本当にいい行事だと思いました。
立見 貴校では近年、生徒たちに身につけさせたい三つの力を、「共創力」「自創力」「発創力」という造語で表現されています。そのなかの、「共創力」を培う行事の代表的なものが、この「しまなみ海道夜間歩行」なのですね。
林 そうです。「共創力」は「競争力」ではなく、多様な立場のステークホルダーと共に新しい価値を生み出す力を意味します。
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎