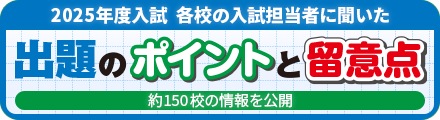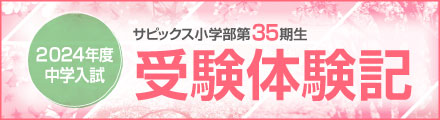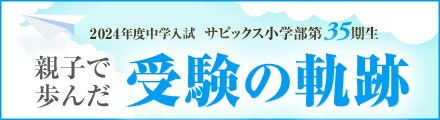さっぴーの社会科見学へ行こう!


アケボノゾウの骨格標本 |
||
|
|
||
| 「展示室は2階だね。らせん状のスロープを上がって部屋に入ると…。おーっ、アケボノゾウの骨格標本だ! これは1985年に狭山市内で見つかったもののレプリカなのか」 | ||
| 「発掘現場の復元模型もあるわ。このアケボノゾウの化石は、ほぼ完全な形で発見された初めてのケースだったのね」 | ||
| 「生命の進化についてのパネルなども並んでいるよ。昔は日本にも恐竜がいたんだよね。もっと化石が発見されればいいのに」 | ||
| 「市内で見られる昆虫の標本もあるわ。狭山市には公園も多くて、たくさんの生き物が見られるのね」 | ||
旧石器・縄文時代 |
||
|
|
||
| 「わあ、土器がたくさんある! 狭山市にも縄文時代の遺跡がいくつもあって、この土器はそこから出土したものなのね」 | ||
| 「古い石器も展示されているよ。入間川のほとりでは、手作りの網に石のおもりをつけて、漁もしていたと考えられるんだね」 | ||
| 「見て、竪穴住居の模型よ。当時の床は円形で、中央に囲炉裏が切ってあったんだ」 | ||
| 「縄文時代の次は弥生時代だけど、市内の遺跡は一気に古墳時代まで飛ぶんだって。弥生時代の狭山市周辺には人が住んでいなかったということなのかな。う~ん、歴史のミステリーだ」 | ||

奈良・平安時代 |
||
|
|
||
| 「このころになると、人々は水はけの良い台地に集団で住むようになったのか。これは奈良・平安時代の村の様子を再現した模型だね」 | ||
| 「当時の農家の内部を再現した模型もあるわ。竪穴住居だけど、床は四角になり、かまどは壁際に移っているのがわかるわね」 | ||
| 「大きな器があるよ。これは古墳時代から平安時代にかけて作られた須恵器。1000℃以上の高温でしっかり焼くから、縄文土器より薄くて硬いんだね」 | ||
| 「あ、和同開珎だ。8世紀初めに発行された貨幣で、全国で使われたんだって。狭山でも見つかっているんだ」 | ||
 狭山の井戸は「すり鉢型」
狭山の井戸は「すり鉢型」
井戸の工事は大仕事。特に狭山周辺は地層が崩れやすく、昔は垂直に掘ることが難しかったんだ。そのため、まずは大きくらせんを描いて地面を掘り、すり鉢状の底に井戸を設けたんだね。 これが「まいまいず」井戸で、展示室には市内に残るその一つ「七曲井」の模型もあるのでチェックしてみて。ちなみに、博物館の1階と2階をらせん状のスロープでつなぐ構造も、「まいまいず」井戸をイメージしたものだよ。
これが「まいまいず」井戸で、展示室には市内に残るその一つ「七曲井」の模型もあるのでチェックしてみて。ちなみに、博物館の1階と2階をらせん状のスロープでつなぐ構造も、「まいまいず」井戸をイメージしたものだよ。

◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎