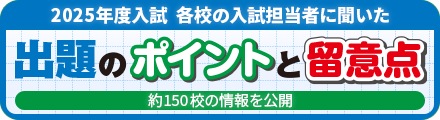さぴあインタビュー/全国版
自由を尊重する理念の下
広がる「新しい学びの世界」が
次代を先導する力を養う
慶應義塾中等部 部長 松本 守 先生

2020年の「SDGs宣言」を機に
教科の枠を超えた学びが浸透

サピックス教育事業本部
本部長
広野 雅明
髙宮 中等部では2020年に「SDGs宣言」をしました。単に環境問題に取り組むだけでなく、SDGsの視点に立った幅広い取り組みをすることだと思いますが、具体的にはどのような内容なのでしょうか。
松本 3年生は週2時間の選択授業があり、そこでは教科の枠を超えた多彩な内容の講座を設けています。教員の専門や特技を生かしたものもあります。そのなかにSDGsと結びつけた視点で取り組む講座もあって、わたしもその一部を担当しています。2年前から、生ごみを資源に変える「コンポスト」を軸に据えて、物質循環をテーマにした授業を展開してきました。今年は、コンポストを使ってハツカダイコン(ラディッシュ)を育てました。今の子どもたちは、種をまいて野菜を育てる経験などしたことがないだろうと思って取り入れました。無事に収穫できたので、「これをどうしたい?」と生徒に聞いたら、「自分たちで料理して食べたい」と言うので、急きょ家庭科室で調理することになりました。そうすると、ラディッシュの赤い部分に疑問を持ち、自分で調べて「アントシアニンが含まれている」と言ってきた生徒もいました。そんなところから学びは広がっていきます。見たこと、聞いたことはあっても、実際に体験することで知識は深まり、興味・関心も広がります。このような機会を設けることはとても大切です。
広野 国語の先生がダイコンを題材に選ぶとは、確かに教科の枠を超えています。講座のテーマは先生方が自由に決めているのですか。
松本 何をやってもよいというわけではありませんが、自分の専門にかかわることになると、教員の裁量に任されます。たとえばわたしは「SDGsと書道」という講座を持ち、書道がどうSDGsとかかわりがあるかを生徒と一緒に考えています。そのなかでダイコンをすりおろして、それを使って紙に書いてみたり、あぶり出しをしてみたりして、色が変わったらその理由を化学的に調べる、というように学びが発展していきました。
17講座ある選択授業のなかには「ミツバチの世界へ、ようこそ」という講座があるのですが、学内で実際にミツバチを飼育し、専門家の方に来ていただいてハチミツの収穫もします。自分たちで巣を外して蜜の部分を削り取り、遠心分離機のような機械にかけるわけです。そのハチミツは自分たちで食べたほか、地元のお店の協力を得て、ハチミツをまぜたクッキーを特別に作ってもらいました。
髙宮 大学生と共同で行うプログラムもあると伺いましたが、どのような内容ですか。
松本 「気候変動プロジェクト」がそうですね。これは、2021年に開館した慶應義塾ミュージアム・コモンズ(ケムコ)という施設とコラボレーションしたもので、中等部生のほか慶應義塾大学の学生や大学院生も参加して、一緒にワークショップなどを行いました。ケムコのコンセプトは「空き地」で、さまざまな世代が交流できる場になっています。そこで何をやるかは生徒や学生たちが考えて決めます。
生徒たちは、教員よりも、年齢の近いお兄さん、お姉さんの話に興味津々で、言うこともよく聞きます。大学生に直接いろいろなことを教えてもらうと、文字で書かれたものを読むより伝わるようです。それに対して、中学生は「自分はこう考えます」と言いたいけれど、ことばを十分に持っていません。知らないだけなんですね。「それって、もしかしてこういうことなんじゃないの?」と大学生が言うと、そのことばをどんどん使い出し、学校でも友だちにそうした話ができるようになります。その意味でも、このプログラムは生徒たちの大きな刺激になっていると思います。
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎