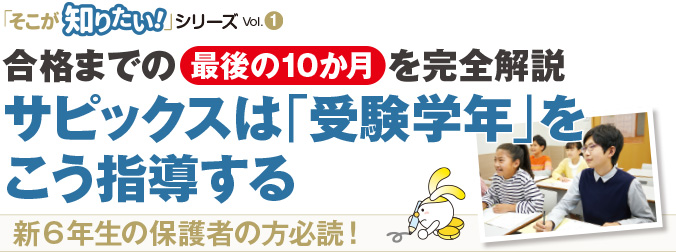そこが知りたい!
目的別に行う保護者会
学習サポートや出願準備などの説明のほか
保護者からの相談・質問にも個別に対応
秋以降はSS特訓や公開模試が始まり、受験生にとって慌ただしい日々が続きます。この時期には、保護者の方の役割がいっそう重要になります。サピックスでは、9月と11月に保護者会を開催し、それぞれの時期に保護者の方がやるべきことや、あらかじめ理解しておくべきことをご説明します。
9月の保護者会では、SS特訓や過去問への取り組み方、入試本番に向けた学習の指針についてお話しします。特に、合格への鍵を握るSS特訓については、授業の進め方や効果的な復習の方法、平常授業や土特とどのようにつながりを持たせるかなどについて、各校舎の校舎責任者や授業担当者が詳しく説明します。
一方、11月の保護者会は入試直前対策のために開かれます。本番を迎えるに当たっての注意点や、出願時における注意点などについて、具体的にお話しします。出願のためのお子さまの写真撮影など、保護者の方がやらなくてはならないことは少なくありません。近年、ほとんどの学校で導入されたウェブ出願の注意点などもご説明しますので、入試までのスケジュールを立て、ミスを防止するためにも、ぜひご参加ください。
全体的なスケジュールや必要事項は保護者会でひと通り説明されますが、溝端先生は「何か心配なことや疑問に感じることがあったら、遠慮なく所属校舎にお電話ください」と言います。「不安を感じたら早めに相談してください。お子さんの状況を話してくだされば、どう対応したらよいかが見えてきます。お子さんを指導することと、保護者の方からのご相談に対応することは、われわれ講師の最も重要な仕事です」
冬休みから入試本番まで
こつこつと努力した受験生は強い
入試の直前・本番もふだんどおり取り組む

首都圏の校舎では、冬休みには冬期講習と正月特訓によって総仕上げを行います。冬期講習は年末から年始にかけて合計6日間、13時30分から18時50分まで、正月特訓は12月30・31日と1月2・3日の4日間、9時から17時40分まで行います(※)。いずれもSS特訓と連動した志望校別コースに分かれて受講します。
こうして、入試当日に最大限の実力を発揮できるように調整し、いよいよ本番を迎えます。年明け早々には、地方にある寮制の学校の首都圏入試が行われるほか、一般入試も茨城県・埼玉県・千葉県の順に始まり、関西でも1月中旬に入試が実施されます。そして2月1日からは、東京都・神奈川県の学校が入試を行います。
この時期には試験を受ける一方で、併願する学校の出願準備、入試当日の流れの確認なども必要になるので、家族が協力して取り組まなければなりません。
サピックスでは、平常授業・土特・SS特訓と、入試日直前まで生徒をバックアップし、学力の維持・向上を図ります。また、思うような結果が得られなかった生徒に対して、励ましの電話をかけ、次の入試に向けてアドバイスをするのも講師の役目です。一人ひとりが納得のいく進路を見つけられるまで、全力でサポートを続けます。
以上が、サピックスの「受験学年」の1年間です。受験本番まであと10か月。お子さんも保護者の方も、だんだんと不安や緊張が高まっていくことでしょう。
溝端先生は、「入試本番で大事なのは、『ふだんどおりに取り組む』ことです。ふだん以上のことをしようとすると、かえって硬くなってしまいます。入試直前期の勉強も同じです」と、入試が近づいてもふだんどおりに取り組むことの重要性を強調します。「勉強とは、どこまで歩みを進めたとしても、必ずわからない点や知らない点が残るので、『もう大丈夫。完璧だ!』という状態にはならないものです。入試においていちばん強いのは、こつこつと努力を積み重ねた受験生です。お子さんが十分に力を発揮できるよう、サピックスは全力でサポートします。何か迷ったり不安になったりした場合は、遠慮なくわたしたちを頼ってください。問題点は早いうちに対処したほうが、解決が早くなるものです。有意義な受験にするために、一緒にがんばりましょう!」と締めくくりました。
※講習や特訓の日程および時間帯は、年度により異なることがあります。
お子さまの「いま」を認めることが良いサポートのコツ
成功のコツは「前向きさ」と「プラスイメージ」
わたしは、物事をうまく行うコツは、「前向きな姿勢」と「プラスイメージを持つこと」であり、声掛けをする際には、この二つを引き出せるようにすることが大切だと考えています。
ところが、実際は真逆のケースが多く見られます。
保護者の方は、「受験で失敗してほしくない」と思うあまり「欠点を直そう」と考えがちです。そして、その考えが強くなり過ぎると、欠点の指摘を繰り返してしまって子どものやる気をそぐ結果になることが珍しくないからです。
大人でもそうですが、自分の欠点ばかり指摘されると、モチベーションは上がらないものです。では、どのようにすればよいのでしょうか。今回はポイントを二つ挙げたいと思います。
プラスイメージを含むことばを意識的に用いる
一つ目は、プラスイメージを含むことばや言い回しを意識的に用いることです。たとえば、「欠点」と言いたくなるところは「課題」と言い直す。「○○が欠点」と言われると、悪いところを指摘された感じがありますが、「○○が課題」と言われると、良い方向に向かうために必要なことと聞こえます。
このように、お子さんがプラスにとらえられるような表現を多用することは、モチベーションを高め、能力を伸ばすことに役立つというのがわたしの意見です。
「共感力」を高めることが良いサポートをする鍵
二つ目は、「共感力」を高めることです。叱咤激励は、一段高い立場から行ってもなかなか相手に響かないことが多いものです。たとえば、積極的に勉強に向かおうとしない子に対して、「勉強しなさい!」「そんな態度では合格できないよ」「もっとがんばって!」と言うだけでは、根本的な解決にはならないでしょう。
わたし自身のことになりますが、子どものころはこつこつ努力するのが苦手でした。ですので、反復演習を「面倒」と思うこの気持ちはとてもよくわかります。そうしたこともあり、わたしが勉強を嫌がるお子さんに改善を促す際は、「確かに面倒だよね」というところから話を始めることが多いです。そのうえで、スポーツ選手の例などを挙げ、「おもしろくないことでも活躍するためにやらなければならないことはあるよね。勉強も同じだよ」というように話をします。
このような話し方をすると、一方的に注意するよりも格段によく話を聞いてくれますし、すぐに改善しなくても、こちらが伝えたいことはわかってくれることが多いです。
お子さんの今の状態のなかで、保護者の方が「共感」できるポイントをぜひ探してあげてください。そして、そのポイントに共感しつつアドバイスをしてあげることが、良いサポートにつながっていくはずです。
小学部事業本部長 溝端 宏光
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎