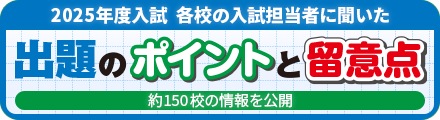子育てインタビュー
ことばの最前線で生きる歌人からのメッセージ

楽しみながら「ことばの力」を鍛え、
未来を切り開く原動力に
記録的なベストセラーとなった『サラダ記念日』(河出書房新社)で知られる歌人であり、エッセイにも多くの著作がある俵万智さんの最新刊、『生きる言葉』(新潮社)が話題となっています。なぜ今、ことばを使う力を高めなければならないのでしょうか。「ことばが大好き」という俵さんに、ことばの重要性や表現力を高める方法、さらには短歌の楽しみ方などについて伺いました。
ことば遊びで語彙力を高め、
人との交わりで表現力を鍛える
広野 『生きる言葉』には、ご自身の子育てエピソードも盛り込まれています。俵さんはお子さんの表現力を磨くために、どんなことをされていましたか。
俵 わたし自身、ことばがすごく好きなので、息子が小さいときから、親子でいろいろなことば遊びを楽しんでいました。しりとりをしたり、「さんずいのつく漢字を集める」競争をしたり…。もちろん、大人と子どもでは語彙力に差があるので、子どもには新聞1枚をわたして、「ここから探していい」といったハンディキャップを設けるなどします。そうやってことば遊びをしていると、しりとりに勝ちたくてことばを集めたり、新聞に興味を持ったりして、どんどん子どもの語彙が増えていきました。
語彙力が高まったことで、国語以外の教科にも好影響があったように思います。算数にしても社会や理科にしても、教材や問題は日本語で書いてありますから、やはりことばの力はすべての教科の基本になるのでしょうね。
広野 お子さんが小学生時代は石垣島で過ごされたそうですね。島での生活は表現力を鍛えることにつながりましたか。
俵 島に行くまでは、ゲームをやりたがって、それをどう制限するかが悩みの種でした。ところが、石垣島に引っ越したら、まったくゲームをしなくなりました。島の自然のなかで友だちと思いきり遊ぶのが楽しかったのでしょうね。「最近ゲームにさわらないね」と聞いたら、「だって、オレが今、マリオなんだよ」という答えが返ってきました(笑)。自分がゲームの主人公になったような気持ちで自然のなかで冒険をしている、その実感がこもったセリフです。息子ながらうまいこと言うなと思って、歌集のタイトルにもしました。
広野 自然との触れ合い、友だちとの遊び、どれも今の社会ではなかなか経験できないことですね。
俵 小学校高学年になると、親元から離れて山のなかで過ごすキャンプに送り出すようにしました。その間は子どもとまったく連絡が取れないので気が気ではないのですが、主催者の方から「親の知らない秘密を持つことも大事な年齢です」と説明され、「そろそろ親離れ、いや、わたし自身が子離れをしなくては」と覚悟するようになりました。親の庇護から離れ、異年齢の子たちと過ごす経験は、コミュニケーション能力を鍛えるうえでも貴重だったと思います。
子どものチャレンジ精神を尊重し、
支えることが成長につながる

新潮社(東京都新宿区)会議室にて
広野 お子さんは、受験して全寮制の中高一貫校に進学されました。どのような思いがあったのでしょうか。
俵 息子にとって石垣島は天国のような場所でしたが、地元の中学は生徒が数名という規模です。中学生になったら大人数のなかで揉まれたほうがいいのではと考え、いろいろな方に相談したところ、「宮崎にもユニークな学校がたくさんあるよ」と教えてもらいました。わたしとしては、市街地の進学校に親元から通ってくれたらいいなと考えていましたが、息子が山奥にある全寮制の県立五ヶ瀬中等教育学校をいたく気に入ってしまったのです。こつこつ勉強するタイプではない息子が、目標が決まったとたんに見違えるように勉強に取り組むようになりました。通塾が難しいので、勉強はわたしがサポートしました。国語は楽しく教えられましたが、算数はそうはいかず苦労しましたね(笑)。
広野 寮はコミュニケーション能力を鍛えるにはうってつけの環境だという話を、よく耳にします。
俵 寮はスマホ禁止で、生徒たちも「スマホでやりとりする暇があったら隣の部屋に遊びに行けばいい」という雰囲気だったようです。寮で同世代の仲間とああでもない、こうでもないと言い合いながら共同生活を送った体験は、息子のコミュニケーション能力を大きく伸ばしたと思います。もちろん失敗もあったでしょうが、それらを糧にことばを使う力、生きる力を身につけていったのではないでしょうか。
息子が全寮制の学校を選んだときは、正直言って驚き、戸惑いましたが、今振り返れば、その選択は間違っていませんでした。子どもが何かに挑戦しようとするとき、親は不安があっても、あたまから否定してはいけません。まずはそれを受け止め、しっかりとサポートすることが大切です。そして、結果ではなく、過程をきちんとほめるようにしたいものですね。
広野 そうしたなかでこそ親子のコミュニケーションが深まり、子どものことばを使う力も伸びていくのでしょうね。本日は、ありがとうございました。
- 25年11月号 子育てインタビュー:
- 1|2
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎