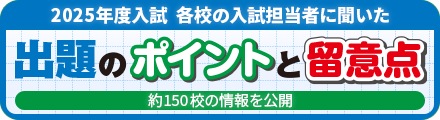子育てインタビュー
ことばの最前線で生きる歌人からのメッセージ
楽しみながら「ことばの力」を鍛え、
未来を切り開く原動力に

俵 万智さんTawara Machi
(たわら まち)●大阪生まれ。歌人。早稲田大学第一文学部卒業。学生時代に歌人で国文学者の佐佐木幸綱氏に師事し、短歌を始める。1988年に現代歌人協会賞、2022年に迢空賞受賞。ベストセラーとなった『サラダ記念日』(河出書房新社)をはじめ、『愛する源氏物語』(文春文庫)、『オレがマリオ』(河出書房新社)、『未来のサイズ』(角川書店)、『生きる言葉』(新潮社)のほか、歌集、評伝、エッセイなど著書多数。
記録的なベストセラーとなった『サラダ記念日』(河出書房新社)で知られる歌人であり、エッセイにも多くの著作がある俵万智さんの最新刊、『生きる言葉』(新潮社)が話題となっています。なぜ今、ことばを使う力を高めなければならないのでしょうか。「ことばが大好き」という俵さんに、ことばの重要性や表現力を高める方法、さらには短歌の楽しみ方などについて伺いました。
SNSが普及した社会だからこそ
磨き上げたい「ことばを使う力」
広野 歌人である俵さんが“ことば”をめぐる思いをつづった『生きる言葉』が今、話題になっています。
俵 ありがとうございます。この本の企画段階では、わたしの生き方について振り返る内容になる予定でした。しかし、出来上がったものに目を通してみると、ことばに関するところにはどうしても手を入れたくなってしまい、「自分の生き方よりも、今はことばについて考えたい」という気持ちが募っていきました。そこで、ことばに絞った内容で一冊書き下ろすことにしたのです。
やはり今の時代、生きる力は、ことばの力と直結しています。SNSが象徴するように、コミュニケーション手段が大きく変わりつつある時代だからこそ、ことばについて考えることがとても大事になっています。この本を多くの人が手に取ってくださっていることに、わたしの思いは間違ってなかったと、大きな手応えを感じています。
広野 SNSでは、短いことばがスピーディーにやり取りされます。だからこそ、ことばの使い方が重要になっているのでしょうね。
俵 今やSNSなしで暮らすことが難しい世の中になっています。誰もが自分の思いを表現できるSNSですが、実はことばを使うという視点からみると、かなり高度なスキルが必要とされます。対面のコミュニケーションであれば、ことばが少々足りなくても表情や声色、身振りなどの非言語的な要素がそれを補ってくれます。一方、SNSのように文字だけが飛び交う世界では、たとえば「まだやってるんだ」ということばが賞賛の意味にも非難の意味にもとらえられ、ともすれば行き違いが起こりがちです。だからこそ、これからの時代を生きていく子どもたちには、ことばを使う力をしっかりと身につけてほしいですね。
広野 子どもたちの間では、メッセージのやり取りですぐに返事を送る「即レス」をしないという理由で、人間関係に支障をきたすこともあるようです。
俵 ことばは、いったん相手に届いてしまったら取り返しがつきません。「さっきのなし」というわけにはいかないのです。だから、たとえ1秒で返信できても、すぐに送らないことです。書いたらひと呼吸置いて、考える時間を取ることが大事です。IT機器を使いこなせることと、IT機器を使ったコミュニケーションが上手だということとは、必ずしも一致しません。そのことを、大人も子どもも気をつけたほうがいいですね。ことばは自分が発した瞬間に、自分のものではなく、相手のものになるというぐらいの気持ちで、慎重に扱うように心がけてほしいと思います。
型があるから親しみやすい短歌
短いことばで自分の思いを的確に

サピックス教育事業本部
本部長
広野 雅明
広野 俵さんが1987年に発表された歌集『サラダ記念日』は、日常の何気ない思いが話しことばで伸び伸びと表現されています。「『この味がいいね』と君が言ったから七月六日はサラダ記念日」をはじめ、どの作品も新鮮で、短歌はルールが多くて堅苦しいというイメージが覆されました。
俵 早稲田大学第一文学部(日本文学専修)に在学中、歌人で国文学者の佐佐木幸綱先生に師事し、短歌の世界に入りました。大学卒業後、神奈川県立橋本高校で国語を教えていたときに、『サラダ記念日』を上梓しました。わたしの歌集を通じて、短歌の楽しさが伝わったのなら何よりです。
実は、短歌をよむことは、短いことばで的確に自分の思いを伝えるのに、すごくいいトレーニングになるので、お勧めです。型があることに窮屈な印象を抱くかもしれませんが、逆に型はとても便利なものなのですよ。短歌や俳句のほかにも、華道、茶道など、日本の文化には型を重視するものがたくさんあります。こうした型は、長い間、多くの人が取り組むなかで、「これがやりやすい」「この方法だと効果的だ」という知恵が集まって生まれたわけです。短歌の型も、日本語で何かを表現するとき、五七五七七にするとリズムよく伝わりやすいから定着したのではないでしょうか。「型さえ踏襲すれは短歌になる」と考えれば親しみが持てますし、肩の力が抜けて気軽にチャレンジできるかもしれませんね。
広野 考えてみると、たとえば万葉集には古代の天皇・皇族から名もなき庶民まで、当時の人々のさまざまな思いが「歌」という形で残っているわけで、これが現代まで伝わっていることは、世界的にみてもすばらしいことですね。
俵 1300年ぐらい前から今に至るまで、ごく普通の人々が短歌をよみ続けているのは誇らしいことですよね。今でも新聞には俳句・短歌のコーナーが掲載され、そこに多くの作品が寄せられています。海外の方にこの話をすると、「日本は詩の大国なのですね」と驚かれます。
広野 日本語の奥深さは文字によるところも大きいのではないでしょうか。中国から伝わった漢字が日本でアレンジされ、ひらがなやカタカナが加わったことで、わたしたちは「山」と書いたり「やま」と書いたりして、細やかなニュアンスの違いを表現しています。しかも近年は、絵文字なるものまで誕生しました。
中学受験短歌
※広野本部長によるオリジナル作品
教材と プリントテスト 計算紙 紙は増えども 点は上がらず
組分けテ 今回こそはと 送り出し 帰りて来ると 秋の夕暮れ
お正月 5月の連休 盆休み 世間の休みが 勝負の山
塾弁は 数日だけは バランスを 我が子望みし 唐揚げとカツ
※生成AIによる作品
春待てば 未来の扉 ひらかれて 学びの道を ともに歩まん
秋風に うなだれ帰る 子の肩を 支え励ます 父母のぬくもり
師走空 祈りを込めて 背を押せば 最後の伸びよ わが子に宿れ
六年の 日々を積みきて いま立てり 受験の門に 子を送り出す
俵 絵文字は、SNSやメールで文字だけのコミュニケーションをする際に、ニュアンスを補い、伝える意味でとても有意義な工夫だと思います。
広野 最近話題の表現ツールといえば、生成AIの存在も気になるところです。試しに受験短歌を作らせてみると、短い時間でいろいろな歌をよんでくるので驚きました。思わず自分も、日ごろの塾生の様子を思い浮かべながら作ってみたんですよ(笑)。
俵 さすがに塾の先生はよく見ていらっしゃいますね。特に秋の夕暮れの作品などは、組分けテストが返ってきたときのたそがれた気分がうまく表現されていて、とても気に入りました。心情は、直接的なことばで表現するよりも、夕陽など何かに気持ちを託したほうが相手に伝わりやすくなるものです。
一方、AIでも確かに短歌を作ることができます。しかし、AIを使うと、ことばを選び、考えるという作業を捨てることになるので推奨できません。短歌作りを通して、自分の考えを自分のことばで文字化する楽しみを知ってほしいと思います。
『生きる言葉』
俵万智 著
新潮社 刊
1,034円(税込)

SNSなどを通じて顔の見えない人ともコミュニケーションできる現代社会は、便利な反面、トラブルにも巻き込まれがちでやっかいでもあります。こうした時代に、ことばの力をどう鍛えたらいいのでしょうか。歌人の俵万智さんが、子育て、SNS、AIなど、多様なシーンでのことばの使い方を、体験を踏まえて考察します。
『オレがマリオ』
俵万智 著
河出書房新社 刊
1,760円(税込)

「『オレが今マリオなんだよ』島に来て子はゲーム機に触れなくなりぬ」――。俵万智さんの第五歌集。東日本大震災を間に挟み、第一部と第二部とに分かれます。縁あって、友人のいる石垣島に引っ越した俵さん親子。そこで出会った自然や人々、伸び伸びと遊ぶ息子さんの姿を短歌によんでいます。
- 25年11月号 子育てインタビュー:
- 1|2
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎