子育てインタビュー
「数学のお兄さん」からのアドバイス

実物に触れ、ときには回り道して
数や図形への理解を深めよう
「子どもを算数好きにするにはどうすればよいのか」。そんな悩みをもつ保護者は少なくないようです。そこで今回は、算数・数学のおもしろさを伝えるために、「数学のお兄さん」として執筆、講演、TV出演、イベント開催など多彩な活動を展開している数学教育者の横山明日希さんにインタビュー。小学校低学年のうちに算数・数学の基礎力を定着させることの重要性やその具体的な方法について伺いました。
学びの途中の「脱線」が
理解を深める契機になることも
広野 パズルのほかに、低学年や就学前の子どもが図形に親しむきっかけとなるものはありますか。
横山 弊社のスタッフはみんな算数や数学が好きなのですが、知恵の輪、あるいはキューブパズルに夢中になってはまった人、数学の難問を通じて考える楽しさに目覚めた人など、そのきっかけは千差万別です。わたし自身は砂遊びでした。砂でどこまで細長い山を作れるか、どこまで削ると崩れるかなどと試行錯誤しているうちに、立体を把握する力が培われていった気がします。ですから、「これ」と決めつけず、いろいろ試してみることが大切です。
砂や積み木、ブロックなど、シンプルかつ多様な図形を作ることができるものを用意しておけば、子どもたちは自分たちで勝手にルールをつくって、工夫しながら楽しく遊び、自然に図形に親しむようになります。
広野 遊ぶ方法や楽しみ方は人それぞれですから、大人はむやみに口を出さないように気をつけたいですね。
横山 ブロックにはお城や乗り物が作れるキットもあり、子どもがその説明書どおりに作らないと落ち着かないという保護者の方もいらっしゃるようです。でも、「こういうものを作らせたい」という気持ちをぐっと抑えて、子どもの自由な発想を見守りたいものです。
机上の学習についても、効率化されたカリキュラムではなかなか取り上げられない「数学の周辺知識」のような話のなかにも、ゼロの発見のような歴史物語や、定理を考えたり単位の由来になったりした人物の伝記など、子どもが興味を示すものがあります。たとえば、ピタゴラスは数学だけが好きだったわけではなく、音楽、宗教、天文学にも関心があったというような話を聞くと、子どもたちの算数・数学への興味が増して、理解がより深まる場合があります。そうした教科教育のなかで優先順位が下げられがちなことにも触れながら、算数・数学の魅力、おもしろさをどう伝えていくか。その方法を考え、実践していくのが、わたしの使命だと思っています。
そこで、まず保護者の方や授業をする先生方にお願いしたいのは、子どもの「脱線」を頭ごなしに叱らないでほしいということです。授業の内容とは関係のない発言の多くは、授業の邪魔をしようとして出たものではありません。授業を受けながら考えて、本当にそう思ったから言っているケースがほとんどです。それに対して大人は、「確かにそういう見方もあるね」と一度肯定してほしいのです。子どもの発言には、子どもなりの疑問や興味が込められています。発言のなかにある発見や疑問を受容しながら、算数に対する関心や理解を深めていくことが大切です。
広野 塾の授業でも、たとえば速さの問題で、「この電車、速すぎない?」と茶化すような声が出ることがあります。実際、テキストでは類値を変えて類題を作るときに、そのような不自然な答えになってしまうことがまれにあります。でも実は、そういう「おかしい」という感覚はとても大事です。入試問題でも現実に即した出題にこだわる学校は少なくありません。
横山 ペンキを塗る面積の問題で、「これ、分厚く塗りすぎじゃん」という声から、体積の話題に発展したこともありました。算数の力は与えられた問題の答えをただ書くだけでは養われません。答えを吟味し、湧き上がった疑問から自分で問いを作って問題を発展させ、その問いに対する計算を自分で見つけ出し、実際に計算して確かめるという、時間的にゆとりのある学びが必要ですね。
「苦手」と決めつけないで
本人自身の成長に目を向けて
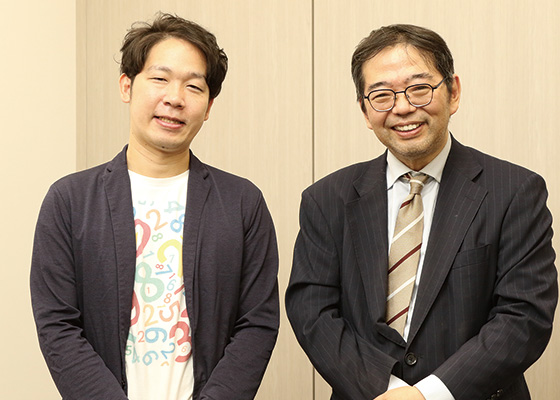
広野 小学校中学年くらいから、徐々に算数に苦手意識を持ち始める子が出てくるようです。そういう子どもたちに対して、横山さんはどのようにアプローチされていますか。
横山 「苦手」と思い込んでいても、単元によっては比較的長く取り組めるもの、集中できるものがあるはずです。そうした単元などを足掛かりに、楽しく取り組める授業を展開するように心がけています。本人が「できた」と思える瞬間や成功体験を積み重ねていくと、3か月から半年ぐらいするうちに変化が出てきます。口では「算数が嫌い」と言いながらも、明らかに取り組む時間や授業での発言量が増えていきますね。
広野 子どもの好き嫌いという感情は、大人が下す相対評価から生まれることが多いものですから、大人は安易にレッテルを貼らないように気をつけたいですね。たとえば、テストの偏差値が4教科のなかでいちばん低い科目が「苦手」「嫌い」と親子で思い込んでしまったりすることはよくあります。ほかの子と比較するよりも、「前より計算が速くなった」「長時間がんばることができた」といった、本人自身の成長をもっと評価してほしいと思います。
子どもは、ちょっとしたきっかけで理解の「回線」がぽんとつながり、一気に成績が上がることがよくあります。そうした瞬間に伸び伸びと羽ばたけるように、自分で問題を解き切る成功体験をこつこつと積み重ね、学力を伸ばす土台を築いていくことが大切ですね。
横山 小学校の算数で学んだことが、中学、高校、大学になって「こういうことか」と理解でき、さらにおもしろくなる瞬間が必ず来ます。今、やっている勉強は中学受験のためではなく、その先につながっているのです。
算数・数学を学ぶのに焦りは禁物です。今、どうしてもわからないことがあるなら、わかるところまで戻ってみることをお勧めします。算数や数学は体系的に積み上げていく学問ですから、それがいちばんの近道です。
広野 算数・数学には「急がば回れ」の精神で取り組みたいですね。本日はありがとうございました。
『サピックス式 タングラム・ハート』
サピックス小学部・サピックスキッズ 著/編集
幻冬舎 刊
2,860円(税込)
※2025年2月下旬発売

10ピースで構成されたハート型の木製タングラムは、サピックスが独自に考案したもの。問題編は「数学のお兄さん」横山明日希先生が担当しています。カイ君とミライちゃんが公園に遊びに行くと、そこには10個のパズルのピースと、「まなびのしま」の地図が落ちていた…。ゲームのような感覚ですごろくを進めていくうちに、空間認識力や図形感覚が身につく、幼児から小学校高学年まで楽しめるパズルです。
- 25年3月号 子育てインタビュー:
- 1|2
◎学校関連リンク◎
◎人気コンテンツ◎














