2005年に中学校を開校して以降、中高一貫教育の基盤を築いてきた大宮開成中学・高等学校では、「愛・知・和」の校訓の下で人間教育を重視した教育を実践。近年は大学合格実績を急激に伸ばし、生徒の力を大きく伸ばす学校として注目を集めています。開校当初から注力する「プレゼンテーション教育」も、新たなステージを迎えています。自主的な学びを深める生徒たちの様子を、探究学習の開発を担当する有田浩之先生にお聞きしました。
中1から高2まで続く探究型の学びで
課題解決力・協働力・発信力を養う
 一貫部探究開発チーム長 有田浩之先生
一貫部探究開発チーム長 有田浩之先生
大宮開成中学・高等学校では、中学開校当初から生徒に探究力・発信力を身につけさせることを目的とした「プレゼンテーション教育」を実践しています。中1から高2までの5年間を通じて、身近な環境や社会課題に向き合い、関心領域について学術的な探究を進め、導き出した考えを発表する機会を重ねていきます。
「小学校教育においても発表の機会が増えるにつれて、プレゼンテーション力をそれなりに持って入学する生徒も増えています。そこで、この10年ほどは、課題解決を通じて社会貢献への意欲を育てることを目標に、総合的な探究学習へと発展させてきました」と、一貫部探究開発チーム長の有田浩之先生は話します。
「面倒見が良い」「真の学力をつける」との評価が高い同校。近年では、プレゼンテーション教育に魅力を感じて入学する生徒も増加していると言います。「とはいえ、誰もが最初から探究テーマを見つけられるわけではありません。だからこそ、“問いを立てる”という力そのものを学ぶ仕掛けを施したカリキュラムにしています」と有田先生は説明します。
中1では身近な環境を、中2では日本社会の課題を取り上げ、いずれもグループで探究を進めていきます。仮説の立て方や検証の仕方、文献検索や調査の方法といった基本的なメソッドを身につけながら、学びを深めていく構成です。たとえば、夏休みには、地球環境・教育・貧困・差別など、SDGsを切り口とした十数冊の課題図書のなかから1人3冊を読むことが課題になります。そのなかで、関心を持ったテーマを軸にグループを編成します。同校では中学入試の成績に応じて、発展的内容を扱うTクラスと、基礎の定着を重視するSクラスに分かれていますが、探究活動ではそれらを超えてグループが編成されるのも特徴です。
「異なるタイプの仲間と協働するなかで、お互いの個性を認め合い、生かす力を育むことが狙いです。自分の得意分野を生かしたり、相手をサポートしたりする場面も多く、協働的な学びが生まれます」と有田先生。各グループには担当教員がナビゲーターとしてつきます。クラス担任以外の教員とかかわることで、人間関係が広がるとともに、教科横断的な視点も身につくと言います。
社会の一員として何ができるのか
広く社会に目を向けるフィールドワーク
探究活動の気づきの糸口となるように、フィールドワークも工夫しています。中2の「奈良・京都伝統文化研修」では、歴史と現代が共存する都市を肌で感じ、日本人としてのアイデンティティーを考える機会となっています。班行動の自主研修日は、探究テーマに沿った見学場所やスケジュールを自分たちで決めます。中3では今年度から「沖縄国際平和研修」が新設。豊かな自然や独自の文化、さらには苦難の歴史をあわせ持つ沖縄を訪れ、国際社会の一員として、平和のために何ができるかを考えます。さらに、高1では全員が参加するオーストラリア研修を通して異文化と出合い、国際的な視野を広げています。
一方、中3からは「世界」をテーマに、いよいよ個人での探究学習が始まります。中1・2でのグループ探究で培った視点をもとに、一人ひとりが関心を持った課題に向き合い、みずから問いを立ててそれを深めていきます。「広く世界に目を向けるだけでなく、社会問題を多角的にとらえ、より良い方向に変えていくにはどうすればいいか、自分なりに答えを出そうとする姿勢を育むことが目標です」と有田先生は説明します。
続く高校では、自由学術研究に取り組み、高2の後半にはその成果を論文にまとめ上げます。「中学のグループ探究では、個人のやりたいテーマに完全に沿えないこともありますが、高校からは自分の進路や関心に合ったテーマに本格的に取り組めます。なかには理系分野で実験を行う生徒もいて、教員の許可の下、校内の実験室も活用しています。また、時には、博物館などの公共施設や企業にみずからアポイントを取り、インタビューや情報提供を依頼する場合もあります。ていねいな文章の書き方や電話対応のマナーなど、社会性が身についていくこともメリットといえます。
 中1・2まではグループ活動、中3からは個人で探究と発表を行います。興味のあるテーマは、おのずと進路意識へとつながっていきます
中1・2まではグループ活動、中3からは個人で探究と発表を行います。興味のあるテーマは、おのずと進路意識へとつながっていきます
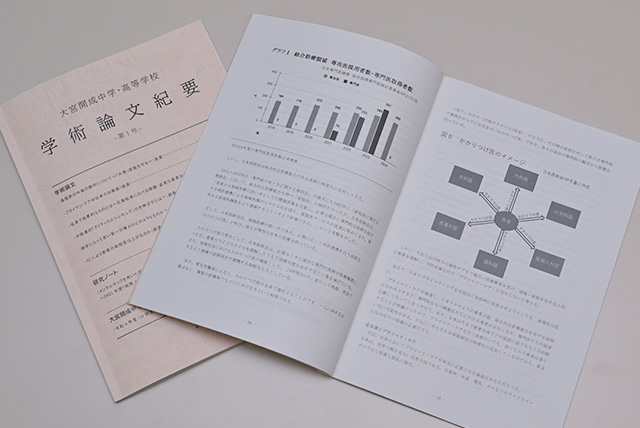 高校での自由学術研究は、最後に論文にまとめます。データを整理し、文章でまとめるスキルは、大学ではもちろん社会に出てからも役立ちます
高校での自由学術研究は、最後に論文にまとめます。データを整理し、文章でまとめるスキルは、大学ではもちろん社会に出てからも役立ちます
「開成文化週間」での発表、高2の論文作成
先輩の雄姿を追い、後輩の手本となる
学年発表会では全グループ・全生徒がプレゼンテーションを行います。そこで選ばれた生徒は、3学期に開催される「開成文化週間」の舞台に立ち、全校生徒の前で発表します。「発表を見た後輩たちは、自分もあのレベルをめざそうと努力しますし、先輩たちは後輩の手本となろうと励むので、年を経るごとにクオリティーが上がります。良い循環が生まれています」と有田先生は言います。近年は1人1台のタブレット所持などICT環境が整い、生徒たちの表現力やプレゼンテーション力にもさらに磨きがかかっています。
総合型選抜や学校推薦型選抜で志望大学に挑む生徒の割合も増えてきた現状を踏まえ、「探究テーマはあくまで生徒自身の興味・関心に基づいて決めてもらうので、こちらから指示や指定をすることはありません。ただ、高1ともなると将来の進路が見えてくる時期でもあるので、方向性が定まっている生徒には、大学入試で生かす可能性も視野に入れて助言するようにはしています」と有田先生。実際に、プレゼンテーション教育の成果をみずからの強みとして、京都大学の特色入試などに挑戦する生徒も増えているそうです。
「今後は企業主催のコンテストや科学オリンピックなど、外部の舞台にも挑戦の幅を広げていきたいですね」と有田先生は展望を語ります。学外での評価や、他校の生徒たちとの出会いを通して、学びの可能性がさらに大きく広がりそうです。

![]()


 一貫部探究開発チーム長 有田浩之先生
一貫部探究開発チーム長 有田浩之先生 中1・2まではグループ活動、中3からは個人で探究と発表を行います。興味のあるテーマは、おのずと進路意識へとつながっていきます
中1・2まではグループ活動、中3からは個人で探究と発表を行います。興味のあるテーマは、おのずと進路意識へとつながっていきます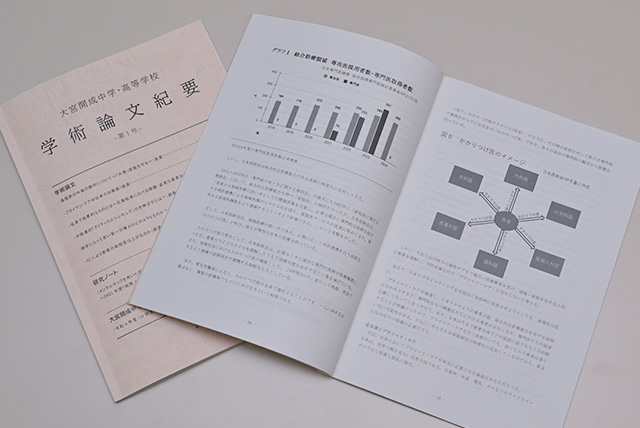 高校での自由学術研究は、最後に論文にまとめます。データを整理し、文章でまとめるスキルは、大学ではもちろん社会に出てからも役立ちます
高校での自由学術研究は、最後に論文にまとめます。データを整理し、文章でまとめるスキルは、大学ではもちろん社会に出てからも役立ちます










